|
| 大竹市小方の亀居公園の“詩の坂道”に建立されている「長良川艶歌・詩碑」です。 |
朝
が
白
々
長
良
川
|
枕
淋
し
や
鵜
飼
い
の
宿
は
|
あ
な
た
あ
な
た
私
を
泣
か
す
人
|
い
ま
は
他
人
じ
ゃ
な
い
二
人
|
添
え
ぬ
さ
だ
め
と
知
り
な
が
ら
|
|
窓
に
夜
明
け
の
風
が
泣
く
|
肌
を
寄
せ
て
も
明
日
は
別
れ
|
あ
な
た
あ
な
た
す
が
っ
て
み
た
い
人
|
酔
う
て
私
は
燃
え
た
の
よ
|
好
き
と
言
わ
れ
た
嬉
し
さ
に
|
|
こ
ゝ
ろ
ま
か
せ
の
鵜
飼
い
舟
|
逢
っ
た
ひ
と
夜
の
情
け
を
乗
せ
て
|
あ
な
た
あ
な
た
や
さ
し
い
旅
の
人
|
誰
に
想
い
を
燃
や
す
や
ら
|
水
に
き
ら
め
く
か
が
り
火
は
|
|
長
良
川
艶
歌
|
|
|
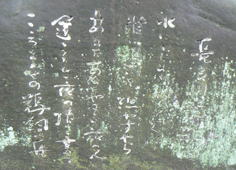 |
|
| * |
1984(昭和59)年に、 石本美由紀作詞、岡千秋(1950- )作曲、五木ひろし(1948-
)唄でヒットしました。 |
|
うかい
鵜飼い |
鵜を飼いならして鮎などをとらせること。また、その鵜を使うのを職業とする人。鵜匠(うじょう)。岐阜県長良川のものが有名。季語は夏。 |
| 長良川の鵜飼 |
1300年前から行われている漁としての鵜飼でしたが、現在は古典漁法を今に伝える観光としての鵜飼となっています。
そのうち、宮内庁の御料場で行われる8回の鵜飼は「御料鵜飼」と呼ばれ、獲れた鮎は皇居へ献上されるのみならず、明治神宮や伊勢神宮へも奉納されるそうです。 |
| 三次の鵜飼 |
戦国時代に始まったとされ、江戸初期、三次藩主の浅野長治が鵜匠制度を確立しました。
見物客に漁を見せる観光鵜飼いは大正時代に始まったそうです。 |
|
| 4番目が「悲しい酒」詩碑で、5番目がこの「長良川艶歌」詩碑です。案内のリーフレットで詩の坂道の道順に行って、すぐにこの詩碑は分かりました。 |
五木ひろしの唄で聞いた事はありましたが、この歌はよく知りませんでしたので、長良川艶歌 ユーチューブで検索して聞きました、そうだったな〜と(わたしは)思った唄でした。
「えんか」を辞書で引くと『「演説歌」からのことばで、明治10年代に、自由民権運動の壮士たちが、その主義主張を歌にして街頭で歌ったもの。のちに政治色が薄くなり、悲恋・心中の人情歌をバイオリン・アコーディオンなどに合わせて歌う遊芸になり、「艶歌」とも書かれるようになった。』とあります。艶歌を「つやうた」と読めばみだらな歌。情事に関する歌。猥歌。春歌。となるようです。歌詞からは情事に関する歌ではあるように思いましたが。 |
| 11.06.11裕・記編集 |
