|
| 中区舟入南の舟入高校に残されている「(被爆した)広島市女の門柱・塀」です。 |
| 市女の門柱 (Municipal Girls School Gate Pillars) |
本校の前身である広島市高等女学校は、1921(大正4)年4月広島市国泰寺町39番地に創設されました。
その後1926(大正15)年3月現在地、船入町沖二ノ割・沖三ノ割・沖十ノ割(現・舟入南1丁目4番4号)に新校舎が完成し移転しました。この門柱はその時校舎東側に設置された正門門柱です。
そして、1943(昭和18)年広島市立第一高等女学校、1948(昭和23)年広島二葉高等学校、さらに1949(昭和24)年広島舟入高等学校と校名は変わりましたが、1957(昭和32)年現在の北側に正門が移るまで、それぞれの正門として多くの女学生・高校生がこの校門から巣立っていきました。
原爆の惨禍にも耐えたこの門柱を、永遠のモニュメントとして残すものです。 |
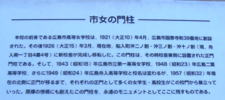 |
|
|
1945(昭和20)年8月6日(月)8時15分、志摩病院上空約580mで爆発した原子爆弾は、爆発の瞬間最高数百万度の火の玉となりました。そして膨張していく火球の表面から発せられた空気の衝撃波(爆風)は、爆心から3〜10kmの間で秒速700m内外のすさまじいものでした(最大級の台風でも瞬間風速は70〜80mです)。
爆風は爆発の3〜4秒後、爆心地から約2.5kmの位置にある当地を襲いました。広島市立高等女学校(市女)の北側の塀は、北北東の方角から爆風を受けた事になります。學校北側周辺には、いも畑が多く、木造家屋がまばらに建っていました。斜めの角度で爆風を受けたために、塀は倒壊を免れましたが、鉄筋コンクリートの塀が波をうった形で残りました。爆風のすさまじさを物語っています。 |
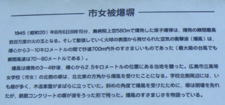 |
|
| ※ |
広島市は被爆建造とは、ということで、被爆建物は爆心地から5km(=5,000m)以内で被爆した建物と規定しています。
また、その他の建造物(ここで取り上げた塀や門柱)は、全壊全焼地域(概ね2km=2,000m)で被爆したものとしていますので、広島市の規定で云えば市女の門柱・塀は、被爆した塀・門柱ではありませんが、被爆の影響を受けたものとして捉えていいのではないかと思い(わたしは)頁を編集しました。 |
|
2011年交流ウォーク探検隊の時ここ広島市立舟入高等学校を(わたしははじめて)訪ねたのです。
わたしは被爆した建物などを訪ねていますが、其れは資料(広島平和記念資料館発行「ヒロシマの被爆建造物は語る」)を参考に、訪ねていましたが、ここ旧・市女(広島市立第一高等女学校)、現在の舟入高校は記述がなかったので訪ねた事がなかったのです。 |
| 11.07.14裕・記編集 |
