|
| 尾道市東土堂町の千光寺公園“文学のこみち”に建立されている「竹田、竹下、伯秀、えい紅碑 」です。 |
| 竹田、竹下、伯秀、えい紅碑 |
| *「えい」の漢字がPCで出てきませんので平仮名にしています |
|
 |
 (エイ) (エイ) |
1.ウズめる。地中にうめる。 2.墓 |
|
| (竹田は)大分県の人。天保5(1834)年2月、尾道に立ち寄り滞在数ヵ月、8月1日に橋本竹下(1790-1862)、亀山伯秀らと千光寺山に登って、花瓶に挿して、たのしんでいた梅の花から石榴(ざくろ)の花までの残花を束ねて、玉の岩かげに葬り盃の酒をそそいで、詩を作り、石に刻んだのがこの碑で、えい紅の碑と名づけた。 |
|
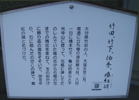 |
|
| 田能村竹田 (たのむらちくでん:1777-1835) |
江戸時代後期の画家。豊後・岡藩医の次男。名は孝憲(たかのり)。字は君彝(くんい)。通称は行蔵。藩校由学館の頭取となる。
藩内の農民一揆の際、藩政改革の建言がいれられず隠退。絵を谷文晁(ぶんちょう)らにまなび,繊細な筆致の独自の画風を確立。幕末文人画壇の代表的な作家。頼山陽(1780-1832)らと親交をもち,詩や書にもすぐれた。作品に「亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)」、画論に「山中人饒舌」。 |
|
「文学のこみち」を下ってきて千光寺の裏手に位置する15番目が河東碧梧桐句碑で、次がこの竹田、竹下、伯秀、えい紅碑で、千光寺境内に入ったところに建立されています。
説明板を読み、この句の「えいこう」の事はそういうことだったのかとおぼろげながら(わたしにも)わかりました。
田能村竹田のことは、頼山陽を知った時に知りましたが、橋本竹下、亀山伯秀については帰宅後尾道の人という事を知りました。 |
| 11.04.14裕・記編集 |
